「花にふれると、心がやわらぐ気がする」
そんな感覚を、科学と文化の両面から育ててきたのが、イギリスという国です。
ガーデニングが国民的趣味といわれるイギリスでは、庭園そのものが人々の心に寄り添う“癒しの場所”。
近年は園芸療法(ガーデンセラピー)の効果が医療や教育の現場でも注目され、花・香り・土といった自然の要素を使ったメンタルケアが実践されています。
この記事では、イギリスに根づく庭園文化と園芸療法の関係性、そして日本でも実践できるセルフケアへのヒントを紹介していきます。
🏡 イギリスに根づく庭園文化と“癒し”の関係

英国の庭園は「鑑賞」より「共に過ごす」場
イギリスの庭園文化は、単なる「美しい景色」を楽しむものではありません。
ガーデンは静かに花を愛で、鳥の声に耳をすませ、“自分に戻る”時間を過ごす場所とされています。
日常のなかに庭があること——それはイギリスの多くの家庭にとって、ごく自然なこと。
都会の小さなテラスでも、地方の広々とした庭園でも、「自然のなかに身を置く」ことは、生活の一部として根づいています。
特に忙しさやストレスが多い現代社会では、こうした“静けさに身を委ねる時間”が、心のバランスを整えるきっかけになるとも考えられています。
自然とのふれあいがメンタルに与える影響
花を育てること。土をさわること。草の香りを吸い込むこと。
これらは、五感を通して脳や自律神経にやさしく働きかける要素だとされます。
たとえば
- 視覚:咲き誇る色とりどりの花々や緑が、気持ちを落ち着ける
- 嗅覚:ハーブや草木の香りが、呼吸を深くし、自律神経をサポートする
- 触覚:土や植物の感触が、感情を落ち着けるリズムにつながる
イギリスではこうした“自然との触れ合い”による心身の調整を、「グリーンケア(Green Care)」という概念で捉えています。
これは園芸だけでなく、森林浴や動物との触れ合いも含む自然由来のケア手法で、予防医療や社会福祉の文脈でも語られています。
🌿 園芸療法(ガーデンセラピー)とは?

イギリス発のホリスティックなケア手法
園芸療法(Horticultural Therapy / ガーデンセラピー)は、植物との関わりを通じて、心と体の回復をサポートするアプローチ。
イギリスはこの分野の先進国の一つで、医療・介護・教育・刑務所など幅広い現場で実践されています。
たとえば、植え替え作業や水やりといったシンプルな作業が、
- 運動量の増加(身体的ケア)
- 達成感や見通し感(認知的ケア)
- 五感への刺激(情緒的ケア)
など、さまざまな側面に作用すると考えられています。
特に、うつ状態、不安感、不眠、ストレスによる疲労といった心理的症状の緩和を目的に、補完的な取り組みとして注目されています(※1)。
また、疾患の有無にかかわらず、日常のセルフケアの一環としても広まりつつあります。
※1 参考文献:
- 「園芸療法の実際と可能性」(園芸療法学会誌)
- “The effects of horticultural therapy on the mental health of elderly people in the UK” – Journal of Therapeutic Horticulture
なお、**園芸療法は医療行為ではなく、あくまで「自然との関わりによるケアの一種」**として位置づけられます。健康への効果については、個人差があることを前提に捉えることが大切です。
医療や教育現場での活用例
イギリスでは、精神科病院、高齢者施設、特別支援学校、リハビリテーションセンターなど、さまざまな現場で園芸療法が活用されています。
具体的には
- 認知症の方の記憶刺激・感情安定に
- 障害のある子どもたちの感覚統合トレーニングとして
- 回復期の患者の日常リズムを取り戻すリハビリ手段として
といった形で、臨床現場に組み込まれているケースもあります。
また、園芸活動は言葉を必要とせず、年齢や国籍、身体状況に関係なく共有できるため、“非言語的な癒し”としての価値も高く評価されています。
とくに注目されるのが、「土にふれること」=“今ここ”に意識を戻すマインドフルネス効果。
手を動かし、植物の成長を見守る時間は、未来や過去ではなく、「今という瞬間」に心を置く練習にもなるのです。
🧑🌾 ナショナルガーデン・スキームと社会福祉のつながり

ナショナルガーデン・スキーム(NGS)とは?
イギリスでは、個人が所有する庭園を年に数日だけ一般公開し、その収益を福祉団体などに寄付するという文化的な取り組みがあります。
それがナショナルガーデン・スキーム(National Garden Scheme, NGS)です。
この活動は1927年から始まり、現在では毎年約3,500の庭園が参加。“癒しの空間を分かち合う”という精神が、多くの人々に静かな感動を届けています。
NGSの公式サイトではこう述べられています:
“Gardens are good for you.”(庭には、人をよくする力がある)
特別なセラピーではなくても、植物に囲まれて静かな時間を過ごすこと自体が、孤独やストレスに寄り添うものだという考え方。
それを社会に還元するこの活動は、まさに英国の“植物福祉文化”を象徴しているといえます。
公共の庭が果たすコミュニティ機能
イギリスでは、図書館や病院、公園などに地域住民が自由に出入りできる「公共の庭」が存在します。
それは「鑑賞用の景色」ではなく、生活の一部としての庭であり、以下のようなコミュニティ機能を果たしています。
- 人と人との非言語的なつながり(言葉がいらない交流)
- 季節を感じる場(感情のリズムを整える)
- 孤立を防ぐ「心の居場所」としての空間
たとえば、ベンチでただ風を感じる。水やりをしながら隣の人と挨拶を交わす。
その何気ない行動の積み重ねが、メンタルヘルスの安定にじんわりと作用すると考えられています。
🌼 植物と香りがもたらす心の安定

代表的な英国の癒しの植物
イギリスのガーデンでよく見かける植物には、香りや成分を活かした“セルフケア”に役立つ種類が多く存在します。
| 植物名 | 特徴と使い方(一般的例) |
|---|---|
| ラベンダー | リラックスを誘う香り。乾燥させてポプリやサシェに。 |
| ローズマリー | スッとした香りが気分転換に。ハーブウォーターや料理にも。 |
| セージ | 鎮静的な香りでお茶やスプレーに。古くから“浄化”の象徴とされる。 |
これらは医薬品ではありませんが、暮らしの中の香りや植物として、感覚を整える存在として親しまれています。
五感を使った“スローな”時間の過ごし方
イギリスの庭園での過ごし方に共通するのは、“五感”を大切にしているという点です。
- 手で土をさわる → 「育てる」という手ごたえ
- 花の香りを吸い込む → 呼吸が深くなる
- 葉や花に目をとめる → 観察する心のゆとり
これらの行為はどれも、今この瞬間に意識を戻す「マインドフル」な時間になります。
日常の中で、植物がそっと寄り添ってくれる。その感覚こそが、英国の庭園文化の本質なのかもしれません。
🌱 日本でも試せる“英国式メンタルケア”のヒント
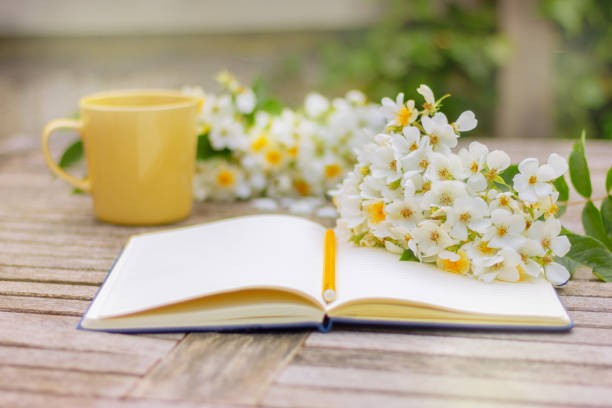
英国のような広い庭がなくても、自宅でできる小さな工夫で“庭の時間”を楽しむことはできます。
🪴 1. 小さな鉢植えから始める
- ラベンダーやローズマリーなどの香るハーブを1〜2種
- 窓辺やベランダでも育てやすく、目に触れることで癒される
🫖 2. 朝夕の「ガーデンタイム」をつくる
- 朝の水やり → 呼吸を深める時間
- 夕方の香りタイム → ハーブティーと静けさで整える
✍️ 3. ガーデンノートをつけてみる
- 花の変化、育てた感想、自分の気持ちの変化など
- 変化に目を向けることで、自分の“心の天気”にも気づけるかも
✨ 結びに
イギリスの人々が大切にする「庭の時間」は、特別な誰かのためのものではなく、自分自身と向き合うためのもの。
植物は静かに、けれど確かに、心の中にある小さな波を整えてくれる存在です。
今日、ほんの少しだけ。
花の香りをかいでみる。
土にふれてみる。
そんな時間が、あなた自身の庭を育てる第一歩になるかもしれません。
🥬 安心・安全な食を日常に。自然栽培の旬野菜を取り入れる暮らし

🥕🌿ミニマルでサステナブルなライフスタイルを実践するなら、「食」の選び方も見直したいもの。
ナチュラルライフをより豊かに、そして環境に優しい毎日へ。
そんな方にぴったりなのが、国内最大級の産直通販サイト【食べチョク】です。
農薬や化学肥料に頼らない栽培方法や、環境保全型農業に取り組む生産者から直接、新鮮な野菜が届きます。
全国のこだわり農家さんとつながることで、食卓も心も満たされる感覚をぜひ体験してください。
🛒そのほかのショッピングサイトで探す場合はこちら:
- ▶ 楽天市場はこちら
- ▶ Yahoo!はこちら
- ▶ Amazonはこちら



